【税理士監修】個人事業主が納める税金は?計算方法・種類・納付時期を解説
【税理士監修】個人事業主が納める税金は?計算方法・種類・納付時期を解説

2025/04/08

2025/04/17
企業と直接の雇用関係を結ばずに事業を営む個人事業主。店舗経営などを行う自営業者や、専門性を活かして独立したフリーランスなど、その形態はさまざまです。
この記事では、個人事業主が支払う必要のある税金の種類や計算方法、納付方法について解説。また、税金の納付タイミングやさまざまな納付手段についても紹介します。
個人事業主が納める主な税金の種類
個人事業主が納める主な税金の種類

まずは、個人事業主が納める主な税金である「所得税」、「住民税」、「個人事業税」、「消費税」の4つについて解説します。
・所得税
1年間(1月1日~12月31日)の課税所得金額に対して課される国税です。「課税所得金額」とは、所得(利益)から事業に関連する経費や各種控除を差し引いた後の所得のこと。所得が一定額以下の場合は、所得税を納める必要はありません。
毎年原則3月15日までに確定申告を行い、振替納税や電子納税、クレジットカード納付などで行います。
・住民税
地方自治体が提供する行政サービス(教育、福祉、消防など)の財源となる地方税です。前年の課税所得金額を基準に算出されます。
自治体から送付される納付書に基づき、年度で4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付、または一括納付をするのが一般的です。口座振替やコンビニ納付も可能です。自治体によっては、クレジットカードでの納付にも対応している場合があります。
・個人事業税
特定の業種に該当する事業を営む、個人事業主に課される地方税です。
特定の事業とは、「地方税法」等で定められた業種(法定業種)のこと。商業やサービス業、農林水産業、製造業、専門職、医療関連職など、多くの業種が該当します。ほかに、不動産所得も個人事業税の課税対象です。事業所得(給与所得や不動産所得などは含まない、事業の所得)から290万円の事業主控除を差し引いた金額に課税されます。
都道府県から送付される納税通知書に基づき、一般的に8月と11月の年2回納付します。口座振替やコンビニ納付を利用できます。
また、個人事業税は事業に関連する支出とみなされるため、経費として計上できます。
・消費税
商品やサービスの提供に対して課される国税および地方税です。消費税は本来消費者が負担する税金のため、対象となる事業者は、売上と合わせて消費者から預かった消費税を消費者に代わり納付する、間接税(税を納める人と納付する人が異なる税金)になります。
消費税を納める必要があるのは、課税事業者として前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合と、インボイス制度により適格請求書発行事業者になった場合などです。
消費者に代わり納付する消費税は、経費の支払いで支払った消費税の相当額分の控除を受けられます。ただし、控除を受けるには取引先から発行された「適格請求書(インボイス)」が必要です。
納付は所得税の確定申告と同時に行うことが一般的で、期限は翌年3月31日までです。振替納税や電子納税、クレジットカード納付などの方法が利用できます。
▼インボイス制度についてはこちらの記事で解説しています
【初心者向け】自分に関係ある?インボイス制度をわかりやすく解説
・資産状況などに応じて納める必要がある税
資産状況などに応じて、納める税金もあります。
たとえば、事業用の土地や建物を所有している場合に発生する固定資産税や、事業用の不動産を新たに取得した際の不動産取得税などです。ただし、事業に関する住宅や土地については軽減措置が適用される場合があります。
また、所得税などの納税期限を過ぎた場合には、延滞税も発生します。
各種税額の計算方法
各種税額の計算方法

個人事業主が納める税金は、それぞれ計算方法が異なります。自身で計算する必要のない税金もありますが、計算方法を理解しておくことで、年間の収支計画を立てやすくなるでしょう。
・所得税
1年間の全ての所得から所得控除を差し引いて算出した課税所得金額に、税率を適用し税額が算出されます。所得税は課税所得により税率が変わる「累進課税制度」が採用されており、所得税の控除額も課税所得に応じて異なります。
【所得税の計算式】
所得税= 課税所得金額※ ×税率-所得税の控除額(「所得税の速算表」で当てはまる控除額)
※ 課税所得金額は、事業の総売上から必要経費を差し引き、さらに基礎控除や扶養控除、医療費控除などの所得控除を差し引いて算出。
【所得税の速算表】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお、2037年までは、原則として基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が追加で課されます。
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率
参考:国税庁「所得税のしくみ
・住民税
個人が支払う住民税(個人住民税)は、各自治体から納付書が送付されるため、個人で税額を計算する必要はありません。ただし、仕組みや計算方法を理解していると、年間の支払い額を事前におおよそ把握できるでしょう。
住民税は、「所得割」「均等割」の合計額が徴収されます。
【住民税の計算式】
住民税 = 所得割+均等割
所得割 = 前年の課税所得×10%(市町村税6%+都道府県税4%)
均等割 = 所得に関係なく5,000円
参考:総務省「個人住民税
・個人事業税
個人事業税は、各都道府県の税務事務所から納税通知書が送付されます。住民税と同じく、個人で税額を計算する必要はありません。納付期限は都道府県によって異なる場合があるため、詳細は都道府県の税務事務所に確認しましょう。
【個人事業税の計算式】
個人事業税額 =(事業所得※ -290万円)×業種別税率
※事業所得は、事業の総売上から必要経費を差し引いて算出。青色申告特別控除額の調整などが必要。
【個人事業税の業種別税率】
| 業種 | 税率 | |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 5% | 物品販売業、製造業、電気供給業、運送業、不動産貸付業、駐車場業、請負業、料理店業など、全37業種 |
| 第2種事業 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業 | 5% | 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、公認会計士業、設計監督者業、理容業など |
| 3% | あんま・マッサージ、はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
| 業種 | 税率 | |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 5% | 物品販売業、製造業、電気供給業、運送業、不動産貸付業、駐車場業、請負業、料理店業など、全37業種 |
| 第2種事業 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業 | 5% | 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、公認会計士業、設計監督者業、理容業など |
| 3% | あんま・マッサージ、はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
参考:東京都「個人事業税
・消費税
消費税は、前々年度(1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円を超える場合、または適格請求書発行事業者に登録している場合などに納税義務が発生します。消費税の計算はいくつか計算方式がありますが、一般的な原則課税方式を紹介します。
【消費税の計算式:原則課税方式】
納付する消費税= 消費者から預かっている消費税-支払った消費税
原則課税方式の場合、消費税10%と8%を分けて計算する必要があるので、注意しましょう。
消費税の計算方法には、前々年度の課税売上額が5,000万円以下の場合に適用できる簡易課税方式、インボイス制度により課税事業者となった場合に適用できる経過措置の2割特例もあります。事業の状況や売上額などを鑑み、どの計算式を適用するのが良いか税理士と相談すると良いでしょう。
参考:一般社団法人 全国青色申告会総連合「個人事業主の消費税
各種税金の納付時期と納付方法
各種税金の納付時期と納付方法

・所得税
納付期日:毎年3月15日まで(土日祝日の場合は翌営業日が期限)。
【納付方法】
納付方法は6種類あります。
1)現金納付:各金融機関や税務署の窓口で納付。
2)振替納税:事前に口座振替の手続きを行うことで、納期限に自動引き落とし。
3)e-Tax:電子申告・納税システム「e-Tax」を利用して納付。
4)クレジットカード納付:国税庁が提供する「国税 クレジットカードお支払サイト」を利用して納付。手数料が必要。
5)スマホアプリ納付:「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付。
6)コンビニ納付(二次元コード):国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報を二次元コードとして作成し、コンビニエンスストアで納付。
参考:国税庁「税金の納付
参考:国税電子申告・納税システム「e-Tax
参考:F-REGI「国税 クレジットカードお支払サイト
・個人事業税
納付期日:年2回の分割納付(8月末と11月末)。
【納付方法】
納付方法は4種類あります。
1)現金納付:各金融機関や自治体窓口で納付。
2)口座振替:事前に手続きを行うことで自動引き落とし。
3)コンビニ納付:納付書を利用。
4)クレジットカード納付:一部地域で対応。納税額の上限や手数料が設定されている場合があります。前述した「F-REGI」のほか、スマートフォンであれば「モバイルレジ」を利用可能。手数料が必要な場合も。
・住民税
納付期日:
1)年4回の分割納付(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)。
2)一括納付:6月末に全額納付。
上記どちらかを選択します。
【納付方法】
納付方法は「個人事業税」と同じです。
・消費税
納付期日:翌年3月31日まで(3月31日が土日祝日の場合は翌営業日が期限)。
【納付方法】
納付方法は「所得税」と同じです。
確定申告の「青色申告」「白色申告」、違いやメリットは?
確定申告の「青色申告」「白色申告」、違いやメリットは?

1年間の所得額に応じて、納付すべき所得税を算出し、納税するのが「確定申告」です。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
・青色申告とは
複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書の作成が必要です。税務署へ「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告での確定申告が可能になります。
青色申告を選ぶメリットは、最大65万円の特別控除(電子申告を行う場合)や、赤字の繰越が3年間可能なこと、家族への給与を経費として計上できる「青色事業専従者給与」の活用が可能なことなどが挙げられます。
貸借対照表と損益計算書を作成する必要があるなど、ややハードルが高く感じられますが、会計ソフトなどを利用すれば、複式簿記や必要書類の作成が自動化され、手間を大幅に削減できるでしょう。
・白色申告とは
白色申告は、単式簿記での記帳が認められ、貸借対照表や損益計算書の提出が不要です。手間は少ないものの、青色申告特別控除が受けられず、原則として赤字の繰越はできません。
参考:国税庁「確定申告
確定申告では、所得控除や税額控除も忘れずに利用
確定申告では、所得控除や税額控除も忘れずに利用

個人事業主が適切に納税額を算出するには、「所得控除」と「税額控除」などの各種控除について、正しく理解することも重要です。
・所得控除
所得控除は、所得税を計算する際に課税対象となる所得から差し引かれるものです。代表的な所得控除には、以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
そのほか、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除など、家族構成や状況に応じた控除もあるので、忘れずに申告しましょう。
・税額控除
課税対象となる「所得」から一定額を差し引く「所得控除」に比べて、「税額控除」は算出後の「税額」から直接一定額を差し引きます。一般的な税額控除には、以下のようなものがあります。
- 住宅ローン控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 配当控除
参考:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし
参考:国税庁「No.1200 税額控除
個人事業主にアメックスの法人カード(ビジネス・カード)がおすすめの理由
個人事業主にアメックスの法人カード(ビジネス・カード)がおすすめの理由

アメリカン・エキスプレス(アメックス)では、法人カードを「ビジネス・カード」と呼んでいます。個人事業主こそ上手に活用したいのが、ビジネス・カードです。
ビジネス・カードを活用することで、事業に関する支払いを一元管理できるほか、付帯サービスの大手会計ソフトとの連携も可能。経費の自動仕分けや、確定申告時のデータ集計がスムーズに行えます。前述した、青色申告に必要な複式簿記による記帳、貸借対照表や損益計算書の作成も、効率的に行うことができるのは大きなメリットです。
ほかにも、さまざまなメリットを享受することができます。
- ビジネスとプライベートの支出の分離:ビジネスとプライベートの支出を、明確に区分けできます。
- キャッシュフローの改善:一括払いだけでなく、分割払いやリボ払いにも対応しているため、キャッシュフロー改善の一助になります。
- 利用額に応じたポイントの獲得:獲得したポイントは、カード利用代金への充当のほか、マイルへの移行、さまざまな商品への交換が可能です。
- ビジネスに関する多岐にわたる優待:空港ラウンジの利用のほか、ビジネス・カードの種類によっては、DELL製品のキャッシュバックなども受けられます。
▼アメックスのビジネス・カードについてはこちらの記事で解説しています
法人カード(ビジネス・カード)の申し込みはオンラインで可能
法人カード(ビジネス・カード)の申し込みはオンラインで可能

アメックスのビジネス・カード申し込みは、公式ウェブサイト上からオンラインで行うことができます。
参考:アメリカン・エキスプレス「ビジネス・カード」
個人事業主がアメックスのビジネス・カードを申し込む際には、以下の書類が必要です。
- 代表者の本人確認書類
本人確認書類として認められるのは、以下の書類です。コピーを提出します。
【本人確認書類一覧】
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 各種健康保険証
- 住民票の写し
- マイナンバーカード(個人番号カード)(表面のみ)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
申し込み後、アメリカン・エキスプレスによる入会審査が行われます。
申し込みからカード受け取りまで、個人事業主の場合、通常1週間程度の時間がかかるため、余裕を持って申し込みを行うようにしましょう。
アメックスのビジネス・カードが個人事業主におすすめの理由
アメックスのビジネス・カードが個人事業主におすすめの理由
個人事業主は、個人の支出とビジネスの支出を明確に分けることで、確定申告の負担を軽減することができます。そこで、ビジネスでの決済にはビジネス・カードの使用をおすすめします。
ビジネス・カードも、個人カードと同様、カードにより付帯する優待や特典が異なります。そのため、事業課題に合うビジネス・カードを選ぶことが大切。個人事業主におすすめのビジネス・カードとして、アメリカン・エキスプレスが発行する3種類のカードを紹介します。

アメリカン・エキスプレス®・
ビジネス・ プラチナ・カード
万が一のサイバー攻撃や情報漏えいなどのリスクに備えることができる「ビジネス・サイバー・プロテクション」や、秘書のように出張や会食の手続きを電話1本で対応してもらえる「プラチナ・セクレタリー・サービス」、カード継続時に得られるラグジュアリーな国内ホテルで利用できる1泊2名分の無料宿泊特典「フリー・ステイ・ギフト」など、多角的なサポートがアメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カードの魅力です。
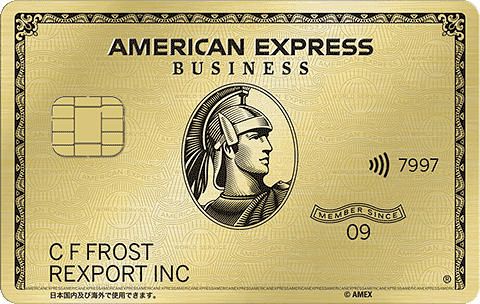
アメリカン・エキスプレス®・
ビジネス・ ゴールド・カード
経費削減に一役買う特典が充実しているアメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード。例えば、デル・テクノロジーズでのパソコンや周辺機器の購入でキャッシュバックが得られる特典をはじめ、キャッシュレス決済導入に役立つ「Square(スクエア)」の決済手数料/月額使用料の優遇など、ビジネスの飛躍を力強くサポートするサービスが備わっています。

アメリカン・エキスプレス®・
ビジネス・グリーン・カード
会計ソフトへのAPIデータ連携や利用料の優遇、車での移動に欠かせないETCカードの無料発行など、本業に集中するための基本機能が揃っているアメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード。ビジネス・カード会員限定のマッチングサービス「ビジネス・マッチング」にも登録可能。定期的に開催されるマッチングイベントは、新規取引先やパートナーの発掘、自社PRにも活用できます。
この機会に、豊富な特典が備わったアメリカン・エキスプレスのビジネス・カードにお申し込みください。













